大野佐紀子「彼女の顔には細部がない・・・アニメの中の描写の落差について」http://d.hatena.ne.jp/ohnosakiko/20110815/1313421598
『借りぐらしのアリエッティ』の背景と人物のギャップについて。「背景の描写が陰影も含めて細かくリアルに描き込まれているのに、そこに登場する人物はベタ塗りでペラッとしていて所謂アニメ絵」。そうか。鈍感なもので、あまり気にならなかった。というか、最初音声を広東語にして観ていたので、広東語もこの絵にけっこう合ってるねなんて思っていた。それはそうと、アニメにおける描写のギャップで気になったのは、原恵一の『カラフル』。風景の描写はフォト・リアリズムの域に達した精密さなのに対して、食べ物の描写に全然リアリティがない。それに伴って、食べるという動作もただ口をもごもごさせているという感じになっている。この映画で食べ物は物語上の重要性を持っているにも拘わらず。
![借りぐらしのアリエッティ [DVD] 借りぐらしのアリエッティ [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/619GzFJxc6L._SL160_.jpg)
- 出版社/メーカー: ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
- 発売日: 2011/06/17
- メディア: DVD
- 購入: 9人 クリック: 164回
- この商品を含むブログ (167件) を見る
![カラフル [DVD] カラフル [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61fQhiYSdGL._SL160_.jpg)
- 出版社/メーカー: アニプレックス
- 発売日: 2011/04/20
- メディア: DVD
- 購入: 2人 クリック: 43回
- この商品を含むブログ (46件) を見る
例えば
といった一般的な答えに満足せず、話を「日本人の欧米コンプレックス」の方へ持ってゆく。たしかに、
▶アニメは美術作品のように絵それ自体では成り立たず、人物を動かすことが前提なので、描き込み過ぎると見辛い。▶ジブリアニメにおいてはキャラクターを重要視していない。一方、背景は世界観を表現しているので描き込まれる必要がある。
▶背景が人物に従属している西洋絵画ではなく、背景と人物が等価の日本画の影響がある(アニメでは人物が動くことにより、その描き込み不足が補填される)。
▶一度描けばよい背景と違い、セル画の(動く)人物は枚数が必要なので、描き込んでいたら質を一定に保つのが難しくなり、費用も膨大になる。(Extracted from http://okwave.jp/qa/q3420984.html#answer)
というのは、様々な人が様々な場所で言っていることであり、私もそうだと思う。〈日流〉(寧ろ〈和流〉というべきか)の亜細亜における成功が「日本というエスニシティorナショナリティの脱色」に大きく拠っていたという話*1にも通じる。ただ、それと『借りぐらしのアリエッティ』の背景と人物のギャップを結び付ける理路はあまりよく理解できなかった。
ただ、私の子どもの頃(60〜70年代)の女の子向けアニメやマンガには、明らかに西洋的なものへの憧れがあった。例えばその少し前の人気イラストレーター中原淳一の少女は明らかにオードリー・ヘップバーンをモデルにしていたし、今も活躍している高橋真琴の少女はどれも西洋風だったし、60年代から70年代にかけての少女マンガの類型化された女の子の顔も、より日本人的なイメージから遠ざかることを目指していた。ヒロインの父親の顔など、日本人よりアメリカ人に近く感じられるような描写も見られた。
それは、その時代の日本人のメンタリティ及び生活文化の中に、欧米へのコンプレックスと憧れがあったからだ。
特に身体と顔についての美の基準は、常に欧米が参照されていた。例えば今盛んに行われている、目を大きく二重にし、鼻梁を高くし小鼻を目立たなくするといった美容整形の方向性も、元は西欧の美(人)を基準にしたものだ。
カリカチュアに起源を発する漫画というのはそもそもリアルを捨ててリアルを得るというところがある。ただ、日本の漫画においてはリアルを捨てずにベタに〈リアル〉を指向した潮流が出現した。所謂〈劇画〉である。日本の〈劇画〉は〈映画への復讐〉という側面を有している。山田洋次が東大法学部卒業、大島渚が京大法学部卒業だったことが示しているように、1950年代において低学歴な人は映画監督になる途を既に閉ざされていた。映画への途を塞がれ、絵の才能があった人たちは〈紙の上の映画〉を始めた。
さて、1980年代の(漫画を含む)所謂サブカルの周辺では、劇画=低文化資本の人が読むビンボー臭い読み物として揶揄する感覚があった。例えば、いしかわじゅんはそうした〈劇画〉のパロディを屡々やっていた。アニメでキャラクターの顔、表情を下手にリアルにすると〈劇画〉になっちゃう。アニメにおける背景と人物の描写のギャップというのは、一方ではカリカチュア以来の漫画の伝統に基づき、他方では〈劇画〉の回避という意図があるのではないだろうか。
ところで、描写精度のギャップというのは、中野美代子先生の日中比較春画論のメイン・テーマでもあったよ(『中国春画論序説』*2)。中国の春画における背景の精密さと肉体の稀薄性。日本の春画における肉体(性器)の突出性。
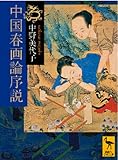
- 作者: 中野美代子
- 出版社/メーカー: 講談社
- 発売日: 2010/08/10
- メディア: 文庫
- クリック: 447回
- この商品を含むブログ (14件) を見る
*1:http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20110805/1312481934
*2:Mentioned in http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20110120/1295539260 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20110711/1310356905 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20110718/1311009859 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20110731/1312137007 http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20110807/1312687458